
『心を映す仮面たちの世界』(檜書店、1996年)という本を読んでいたら、監修をされた故・野村万之丞(追贈:八世野村万蔵)師の文章があり、
演劇は決して「文字のストーリーを立体にしてお見せする」ものではなかったということである。豪華な衣装や仮面で飾られた役者たちが創り出す、非日常の空間にカルタシスを見出すという美学が、明治維新の頃までは「風流性」として日本人の中にあったと思われるのである。
「文学的ストーリーの立体的表現にあらざる」演劇こそ、私たちが本来持っていた演劇なのである
とあり、その後は能『井筒』を例として続いていました。
確かに能や狂言にはそういう要素があると思います。あらすじにしてしまうと、面白さや魅力が欠片すら失せてしまう能や狂言の多いことは前から感じていましたが、生身の人間が演じて作り出すその「場」の力、といったものが能や狂言の魅力の大切な要素なんだと思うのです。
だからこそ、200番前後の古典演目を繰り返していても魅力はあるし、ストーリー展開がほとんどない一部の「仕舞」や「舞囃子」に感動してしまうこともあるんだと思うんです。また、演者によっては見てられないぐらい退屈なものにもなり得る原因も、能や狂言のそんな面によるのではないでしょうか。
立ち方(シテ方・ワキ方・狂言方)はともかく、例えば、私が習ってる大鼓なんて、音は「ドン(小)」と「チョン(大)」の二種類、掛け声は「ヤ」「ハ」「ヨーイ」「イヤ」の四種類しかないわけで、それを八拍子の中のどこに打ち込むかの違いしかないのですから、あまりにも単純といえるわけです。
それが時に感動を与えるのは、生身の人間が作り出す「力」のためなんだと思うんですよね。それは技術も大切ながら、それよりも芸に対する姿勢だとか、かける気合だとか、そんなところから醸し出されると思うのです。私程度の素人がプロに敵わないと感じるのは、そういう箇所なのです。記憶力に頼る私の大鼓ではそういう「力」が出ない。
それは大鼓方に限られることではなく、能全体に通じると思ってます。
野村万之丞師の最初の文章を読んだとき、それを分かりやすく言葉にしていた方だったのではないだろうか、と感じたのです。私は万之丞師の生前の活動には触れることはありませんでしたが、スケールの大きい方だったんじゃないのかな、と思えます。なんだかとても惜しいですよね。
ちなみに今の大河ドラマ「義経」で、オープニングのタイトルバックに「芸能考証 野村万之丞」とありました。後白河上皇がハマっていたという今様などの考証をやってらしたのでしょうか?


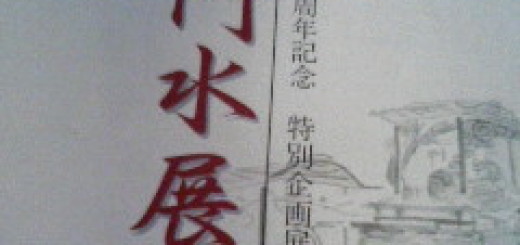


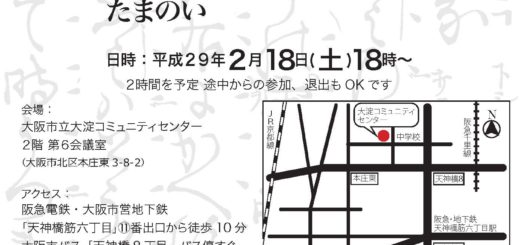
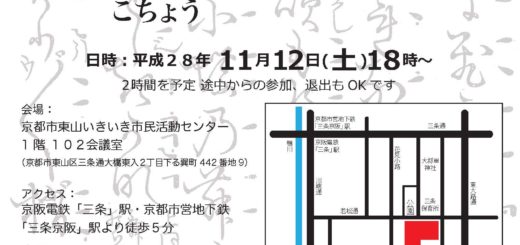


最近のコメント